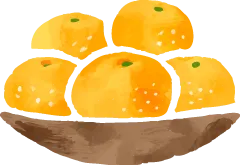皆さん、こんにちは。和歌山県下津町のみかん農家、北文園の北東です。みかんの若葉も色が濃くなり光合成力も上がり、果実もだんだん大きくなってきました。

6月も終わり、いよいよ本格的な夏の到来を感じる今日この頃。振り返ってみると、今年の6月は例年以上に天候に翻弄された一ヶ月でした。梅雨の長雨と晴れ間のタイミングを見極めながら、みかんの木々と向き合う日々は、まさに自然との知恵比べ。今月の作業を通じて改めて感じたのは、適期防除の大切さと、天気予報との睨めっこがいかに重要かということでした。
6月上旬:草刈りと防風樹の手入れからスタート
6月に入って、まず取り掛かったのが草刈りと防風樹の刈込です。5月の暖かさで勢いよく伸びた雑草や防風樹の枝は、放っておくとみかんの木の生育に悪影響を及ぼします。特に防風樹は、みかんの木を強風から守る大切な役割を果たしている一方で、伸びすぎると日照を遮ったり、風通しを悪くしたりする原因にもなります。
この時期の草刈りは体力勝負。朝早くから作業を始めても、日が高くなると汗だくになってしまいます。

6月6日から始まる病害虫との本格的な戦い
6月9日から雨が続くようなので逆算して6月の防除を開始しました。この6月御防除は大事な防除で、梅雨の湿気と気温の上昇により、みかんの木を脅かす様々な病害虫が活発化するタイミングなのです。
今回使用した薬剤は、ジマンダイセン、アドマイヤ、アプロード(荒廃地の隣接園地)を選択しました。
雨媒介の黒点病対策
まず警戒すべきは黒点病です。この病気は雨によって媒介されるため、梅雨時期は特に注意が必要。黒点病に感染すると、みかんの果実に黒い斑点ができてしまい、商品価値が大幅に下がってしまいます。
この病気の厄介なところは、気づいた時には手遅れということも多いのです。だからこそ、予防的な防除が重要になってきます。累積雨量などを見ながら、適切なタイミングで薬剤を散布することで、黒点病の発生を抑えることができます。
ジマンダイセン水和剤:https://www.nissan-agro.net/products/single.php?id=22345
害虫発生消長を読む
6月は害虫の発生消長(季節的な発生パターン)を読む重要な時期でもあります。6月上旬に注意するのは、ヤノネカイガラムシ、イセリアカイガラムシ、チャノキイロアザミウマ、ゴマダラカミキリ、そしてミカンハモグリガです。JA和歌山の下津営農センターでは害虫の発生消長の一覧を用意してくれているので営農指導員に相談しています。
ヤノネカイガラムシは、みかんの枝や葉に寄生して樹勢を弱らせる害虫です。一度大発生すると駆除が困難になるため、発生初期の対策が肝心。この虫の生態を理解し、卵から幼虫になるタイミングを狙って防除することで、効率的に個体数を抑制できます。
ヤノネカイガラムシについて(和歌山県):https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/070109/gaiyou/002/byougaichuzukan/yanone/yanone.html
イセリアカイガラムシも同様に、みかんの木の栄養を吸い取る害虫。特に若い枝を好むため、新梢の伸びる時期には要注意です。この虫が分泌する甘露により、すす病を誘発することもあるため、見た目の問題だけでなく、光合成の阻害という深刻な影響も及ぼします。
イセリアカイガラムシについて(和歌山県):https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/070109/gaiyou/002/byougaichuzukan/icerya/icerya.html
チャノキイロアザミウマは、みかんの新芽や幼果を加害します。被害を受けた部分はキズが大きく残り、果実の品質に大きく影響します。この虫は高温多湿を好むため、梅雨明けの時期には特に警戒が必要です。
チャノキイロアザミウマについて:(和歌山県)https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/070109/gaiyou/002/byougaichuzukan/chanoki/chanoki.html
ゴマダラカミキリは、幼虫が幹の内部を食害することで知られています。成虫による被害は小さいのですが、幼虫が幹を食い荒らして樹を枯らしてしまうのでみかん農家が最も嫌う虫です。成虫の産卵前を狙った防除が効果的で、適期対策が重要になります。
ゴマダラカミキリについて(和歌山県)https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/070109/gaiyou/002/byougaichuzukan/kamikiri/kamikiri.html
ミカンハモグリガは、その名の通り葉を潜葉する害虫。被害を受けた葉は光合成能力が低下し、樹勢の衰弱につながります。特に新梢の展開期には注意深い観察が必要です。
ミカンハモグリガについて(和歌山県):https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/070109/gaiyou/002/byougaichuzukan/hamoguri/hamoguri.html

上記のの害虫に対してアドマイヤを全園に、イセリアカイガラムシの発生園にはアプロードを追加しました。
アドマイヤフロアブル:https://cropscience.bayer.jp/ja/home/product/detail/product18562.php
アプロードフロアブル:https://www.nichino.co.jp/products/query/id2.php?id=88
タイミングが全て:適期防除の重要性
高温多湿で虫が大発生しつつあるタイミングで的確に防除を行う。これが、余計な農薬を使わずに済む秘訣です。害虫の生態を理解し、彼らの弱いタイミングを狙い撃ちすることで、最小限の薬剤で最大の効果を得ることができます。
この考え方は、環境に優しい農業を実践する上でとても重要と考えています。やみくもに農薬を散布するのではなく、科学的な根拠に基づいて必要最小限の防除を行う。これにより、土壌環境への負荷を減らし、天敵昆虫も保護することができます。
しかし、このタイミングを逃すと、害虫の個体数が爆発的に増え、結果的により多くの農薬が必要になってしまいます。一度大発生した害虫を抑制するのは、予防的な防除の何倍も大変な作業になるのです。
ただね、暑いので体力的にきつくなってくるんです。

肥料と微生物の神秘的な関係
今年は5月末に撒いた肥料の分解具合も気になるところでした。有機質肥料を使用している当園では、土壌中の微生物による分解過程が品質に大きく影響します。肥料にきちんとカビ(有用菌)がついて、アミノ酸に分解されるのを待つ時間は、まさに自然の営みを感じる瞬間です。
微生物による有機物の分解は、温度と湿度に大きく左右されます。適度な水分があることで微生物の活動が活発になり、有機物がアミノ酸や無機態窒素に変換されます。このプロセスにより、みかんの木が吸収しやすい形の栄養素が供給されるのです。
雨が降るギリギリの期間で防除を実施したのも、この微生物の活動を妨げないためです。肥料が十分に分解されていない状態で大雨が降ると、せっかくの栄養分が流失してしまう可能性があります。(2023年6月の線状降水帯での水害では肥効が消失してしまったと考えています)
しかし、今年を振り返ってみると、肥料のタイミングにはまだ改善の余地がありそうです。来年はもう少し早めに施肥して、分解期間に余裕を持たせようと考えています。

地域保全会での新たな挑戦
雨が続いた日々には、畑仕事以外の重要な作業もありました。今年から集落の地域保全会の役員として執務することになり、国への補助申請業務も担当しています。具体的には中山間直接支払事業の申請準備です。
中山間直接支払事業は、中山間地域の農業生産活動を継続するための重要な制度です。高齢化が進み、耕作放棄地が増加する中で、この制度により地域の農業と環境が守られています。申請には詳細な資料作成が必要で、パソコンスキルが重宝されるのも事実です。
パソコンが使えるということで様々な仕事を任されることも多いのですが、地域への貢献という観点では、自分のスキルを活かせる良い機会だと前向きに捉えています。これからの5年間、地域の農業振興と環境保全のために力を尽くしていきたいと思います。
若い世代が減少する中で、残された私たちが地域を支えていかなければなりません。IT技術を活用した効率的な事務処理により、本来の農作業により多くの時間を充てることができれば、それは地域全体の利益にもつながるでしょう。

梅雨明けとゾーバー散布の緊急作業
そうこうしているうちに、今年は6月中に梅雨が明けてしまいました。いつも梅雨明けのタイミングで重要になるのが、除草剤ゾーバーの散布です。この除草剤は土壌中の水分がないと効果を発揮しにくいという特性があるため、梅雨明け直後の土壌がまだ湿っているタイミングでの散布が理想的です。
今年は梅雨明けが予想より早く、慌てて散布作業を行いました。ゾーバーは根から吸収されるタイプの除草剤で、雑草の発芽を長期間抑制する効果があります。しかし、土壌が乾燥していると薬剤が根に到達しにくく、期待した効果が得られません。
この緊急作業では、散布後の管理も重要です。薬剤が均一に行き渡るよう、散布パターンを工夫し、重複や散布漏れがないよう細心の注意を払います。また、みかんの木への影響を避けるため、根元から適切な距離を保って散布します。
ゾーバーについて:https://www.mbc-g.co.jp/product/zobar/
天気予報との睨めっこ:先読み農業の重要性
6月を通じて痛感したのは、天気予報との睨めっこがいかに重要かということです。雨に左右される作業が多いこの時期、天候の予測能力が農作業の効率を大きく左右します。
先読みをしながら準備をしておかないと、適期防除を逃したり、雨で薬剤が流されて再散布が必要になったりします。これは経済的な損失だけでなく、土壌環境にも良くない事態を招きます。余分な薬剤使用は避けたいというのが、環境に配慮した農業を目指す私たちの基本姿勢です。
現在では、気象庁の詳細な予報だけでなく、民間の気象情報サービスも活用しています。1時間ごとの降水確率、雨雲の動き、風向きなど、多角的な情報を組み合わせて作業計画を立てます。時には複数の予報を比較検討し、最も確度の高い情報を選択することもあります。
失敗から学ぶ:来年への改善点
今年の6月を振り返って反省すべき点もあります。特に肥料の施用タイミングについては、来年は改善が必要だと感じています。微生物による分解期間を十分に確保し、防除のタイミングとの調整も含めて、より効率的なスケジュールを組む必要があります。
農業は毎年が学びの連続です。同じことを繰り返しているようでも、気候条件や病害虫の発生パターンは年によって異なります。過去の成功体験に頼りすぎず、常に改善点を見つけて次年度に活かす姿勢が大切です。
おわりに:7月への準備
6月が終わり、いよいよ本格的な夏の到来です。7月は枝吊り、摘果作業や夏季防除など、重要な作業が待っています。今月の経験を活かし、より効率的で環境に配慮した農業を実践していきたいと思います。
みかん栽培は、自然との対話でもあります。天候に左右されることも多いですが、それも含めて農業の醍醐味だと感じています。皆さんにお届けする美味しいみかんのために、これからも丁寧な栽培を心がけてまいります。
※当園では、こだわりの和歌山みかんを産地直送でお届けしています。9月末から出荷を始めますのでお楽しみにしてください。 メルマガに登録頂けますと受注開始のご案内をさせて頂きます。宜しければ登録をお願い致します。
メルマガ登録はこちら→https://mikan-kitabun.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new