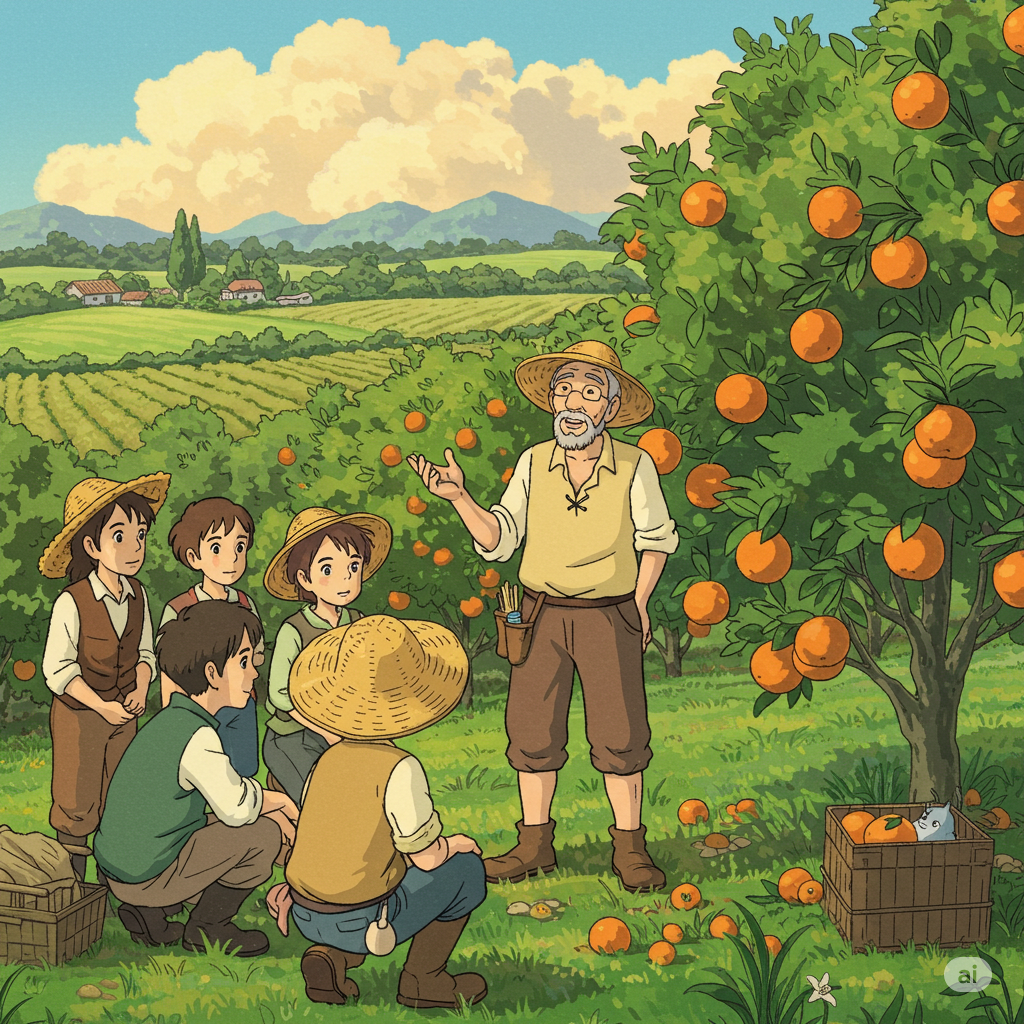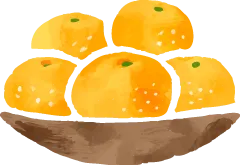北文園の北東です。先日参加した剪定講習会での学びを皆さんと共有したいと思います。昨年の酷暑などの特殊な気象条件から予測する今年の課題まで、みかん栽培の奥深さを再認識する機会となりました。

2024年の気象と2025年の課題
2024年の夏季は酷暑と少雨で非常に厳しい環境でした。重ねて昨年11月は例年にない高温が続き、みかんの生育サイクルに大きな影響を与えました。本来10月末で終わるはずの果実肥大が11月以降も続いたのです。更に早生みかんは着色不良となり収穫が遅れ、樹体の養分が果実に過剰に移行してしまいました。
その結果、樹体養分(炭素C)が乏しくなり、今春は新葉の芽が優勢となり、花芽が極端に少ない状況に直面しています。収穫量に直結する問題ですから、私たち農家にとって大きな懸念事項です。
花芽形成を左右するC/N比
みかんの花芽形成は、樹体内の炭素(C)と窒素(N)の比率によって大きく影響されます。この比率をC/N比と呼び、みかん栽培において非常に重要な指標となっています。
基本的な法則として、C/N比が高い(炭素が多く、窒素が少ない)状態では花芽が形成されやすく、反対にC/N比が低い(炭素が少なく、窒素が多い)状態では栄養成長が促進され、枝葉の生長が盛んになります。
少ない花芽を守るための対策
講師の先生は、このような状況下での肥培管理について貴重なアドバイスをくださいました。
3月末から4月初めに春肥をしっかり行い、樹体の緑化に全力を注ぎました。少ない花でも確実に実らせる取り組みが今年は特に重要なのです。
液肥については4月にはリン酸(P)とカリウム(K)を重点的に与え、最低限の花芽確保に努めました。そして5月には新葉の緑化を促進し、液肥の施用回数は訪花昆虫の時期から5月で4回も実施し、6月以降の生理落下を抑制することに注力されています。
※昨年の夏肥、秋肥をしっかり施用していることはベースにあります。
生理落果とは
みかんの「生理落果(せいりらっか)」とは、果実が自然に木から落ちる現象のうち、病気や虫の被害ではなく、植物自身の生理的な理由で起きる落果のことを指します。生理落果は、みかんに限らず多くの果樹に見られる現象です。6月落果(一次落果)
-
開花・結実後、6月頃に起きる落果。
➡ 花が咲いた後にできた果実が栄養不足などで落ちる。
➡ 木が果実の数を調整していると考えられています。 -
7月〜8月落果(二次落果)
実がある程度大きくなった後の時期に起きる落果。
➡ 高温・乾燥、根の傷み、ホルモンバランスの崩れなどが原因。

肥料コストと効果のバランス
肥料価格の高騰は農家共通の悩みですが、講習会では興味深い見解が先生から示されました。例えば窒素成分8%と7%では、わずか1%の差ですが、効果は倍近く違うこともあるとのこと。つまり、質を高めて量を減らすという選択も有効です。
講師の先生は「肥料代は昨年の売上の1割を使う」という明確な方針をお持ちでした。これは長年の経験から導き出された方針なのでしょう。
師曰く「しっかりご飯を食べさせないと、いい仕事をしてくれない」
安定収量のための施肥と剪定の関係
「しっかり施肥をした上でないと適切な剪定はできない」という指摘は非常に印象的でした。実際、昨年夏肥をしっかり施した園地では、今年も一定の着花が見られるそうです。猛暑に耐えうる樹体づくりがいかに重要かを再認識しました。
また肥料選びでは、NPKだけでなく微量要素の重要性も学びました。コストが安い液肥には微量要素が欠けていることがあり、結果的に効果が半減してしまいます。目先のコスト削減が無駄遣いになりかねないという視点は目から鱗でした。
次年度を見据えた剪定のタイミング
先生の考え方では、翌年「表年」(着花が多い年)になる木は、前年秋に剪定(予備枝剪定)することで着花量を調整できます。実際、10月に行う秋の剪定の時は果実が着果しているので、「来年どれくらい花があるのか?」「どこに芽を出したいのか?」がわかりやすく秋の剪定が適しています。
また、それでも春に花ばかり咲く木は、一樹当たり10カ所ほどの水平枝で花を摘んでおくと翌年の結果母枝になるというテクニックも伝授いただきました。
剪定について過去のブログ → https://mikan-kitabun.com/202503pruning/
JA剪定解説動画 → https://www.youtube.com/watch?v=pLR6YMVTvXE
みかん栽培は一年だけでなく、複数年のサイクルで考える必要があります。今年の難局を乗り切りながら、来年以降の安定生産も視野に入れた管理が求められています。
下津町の気候に合った独自の栽培技術を磨きながら、これからも高品質なみかんづくりに励んでまいります。皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。