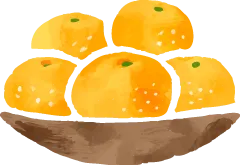こんにちは、北文園の北東です。6月に入り、梅雨の合間を縫って畑の観察を続けています。この時期のみかん畑は、まさに生命力に満ち溢れた季節で、新しい命の息づきと世代交代の物語が同時に展開されています。今回は、6月初旬の畑の様子を詳しくお伝えし、みかんの木々が見せる自然の営みの美しさと複雑さをご紹介したいと思います。
若葉の成長 – 色濃く張りのある新緑
6月の畑を歩くと、最初に目に飛び込んでくるのは若葉の力強い成長ぶりです。5月に芽吹いた新緑の葉が、日に日に色濃くなってきています。初々しい黄緑色から、しっかりとした濃い緑色へと変化していく様子は、まさに生命力の象徴です。
若葉の表面には張りが出てきて、薄くて頼りなかった新芽の頃から比べると、見違えるほどたくましく成長しました。
特に印象的なのは、葉先が空に向かってピンと立っている姿です。まるで太陽の光を求めて手を伸ばしているかのような、力強い向上心を感じさせます。
葉の巻き加減に隠された自然の知恵
よく観察してみると、若葉は少し巻き加減になっています。平らに展開するのではなく、わずかにカールしているのです。最初はなぜだろうと疑問に思っていましたが、これは全方向から日光を効率よく受けるための、植物が持つ巧妙な仕組みなのです。
平らな葉では、太陽が真上にある時しか最大の光を受けることができません。しかし、わずかに巻くことで、朝の斜めの光も、夕方の傾いた光も、より多くの表面で受け止めることができます。また、強すぎる日差しの時には、この巻きが日陰を作り、葉焼けを防ぐ効果もあります。
自然界の植物たちは、人間が思いつかないような精巧な仕組みを何千年もかけて進化させてきました。みかんの葉の小さな巻きひとつにも、そんな長い歴史が込められていると思うと、深い感動を覚えます。

世代交代の物語 – おじいちゃん葉の引退
若葉の勢いある成長とは対照的に、畑のあちこちで黄色く枯れてきている葉を見つけることができます。これらは2年前の旧葉、いわば「2代前のおじいちゃん」にあたる葉っぱたちです。
みかんの葉には寿命があり、通常2-3年でその役目を終えます。この黄色くなった古い葉たちは、光合成能力が低下し、もはや木全体に貢献できる力を失いつつあります。しかし、彼らは最後の最後まで重要な役割を果たしています。
これらの古い葉は、若葉が十分に成長するまでの間、蓄積していた養分を木に供給し続けます。まさに人間社会の祖父母が孫の成長を支えるように、植物の世界でも世代を超えた支援が行われているのです。若葉(孫世代)が立派に成長し、光合成能力を十分に発揮できるようになったのを見届けて、安心して落葉していくのです。
この自然の営みを見ていると、植物の世界にも家族愛のような温かさがあるように感じられます。効率だけを追求するなら、古い葉はすぐに落としてしまえばよいのかもしれません。しかし、みかんの木は世代をつなぐバトンタッチを大切にし、確実に次世代に命をつないでいくのです。

若葉を脅かす病害虫の影
順調に成長している若葉ですが、よく観察すると問題も見つかります。いくつかの葉に、そうか病特有の小さなぶつぶつが現れています。
初期段階では小さなぶつぶつですが、放置すると拡大し、葉の光合成能力を著しく低下させます。また、果実にも感染すると商品価値を大きく損なうため、この時期の観察と早期対応が重要です。

和歌山県農作物病害虫防除所 そうか病について:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/072000/d00216407_d/fil/r6gijyutujyouhou5.pdf
和歌山県編集 かんきつ病害虫図鑑
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/070109/gaiyou/002/byougaichuzukan/zukan.html
エカキムシが描く「ナスカの地上絵」
さらに注意深く葉を見ていると、奇妙な白い線が葉の表面に描かれているのを発見します。これはハモグリガ、通称エカキムシによる食害の跡です。幼虫が葉の内部を食べ進むことで、まるで誰かが筆で線を描いたような模様が現れます。
この食害跡の模様は、時にナスカの地上絵のような複雑で美しいパターンを描きます。芸術的な美しさすら感じさせる模様ですが、農家にとっては深刻な問題です。エカキムシの食害は葉の光合成能力を低下させ、ひどい場合には葉を枯らしてしまいます。
エカキムシは非常に小さな蛾の幼虫で、葉の表皮の間に潜り込むため、外からの薬剤が届きにくく、防除が困難な害虫の一つです。予防が最も重要で、葉の早期の緑化と成虫の発生時期を見極めた適切なタイミングでの防除が必要になります。

果実の成長と生理落果の自然淘汰
葉の観察を終えて果実に目を向けると、小さいながらも確実な成長を確認できます。指の爪ほどの大きさまで育った幼果が、枝にしっかりと付いています。まだまだ小さく、青々とした硬い果実ですが、既にみかんの形をしており、秋の収穫への期待を抱かせてくれます。

しかし、すべての果実が順調に育っているわけではありません。一部の果実は黄色く変色し始めています。これは生理落果と呼ばれる自然現象で、木が自分の力で育てることができる適正な数に果実を調整している過程です。
みかんの木は春に非常に多くの花を咲かせ、多数の果実を着けます。木自身が判断して、より良い条件の果実を選び、余分な果実を自然に落としていくのです。これは植物の持つ驚くべき自己調整能力の現れです。
黄色く変色した果実は、やがて自然に落下します。一見もったいないように思えますが、これにより残った果実により多くの養分が集中し、品質の高いみかんが育つことになります。自然淘汰の原理が、果実の品質向上にも働いているのです。

地表で進む肥料の変化 – カビの力でアミノ酸変換
地面に目を向けると、5月末に施した肉カス有機配合肥料の変化を観察することができます。表面にはうっすらと白いカビが生え、特有の肉の匂いもほとんど消えています。これは非常に良い状態で、カビによる肥料の分解が順調に進んでいることを示しています。
肉カス肥料に含まれるタンパク質は、土壌中のカビ(糸状菌)の働きによってアミノ酸に分解されます。アミノ酸は植物の根が直接吸収できる形の窒素源で、化学肥料の硝酸態窒素とは異なり、植物にとってマイルドで持続的な栄養供給となります。
このアミノ酸による栄養供給は、みかんの味に大きく影響します。急激な栄養供給ではなく、緩やかで持続的な栄養供給により、果実の糖度と酸味のバランスが向上し、深みのある味わいが生まれます。
この夏肥の効果は、まさに今年のみかんの味を決める重要な要素です。カビの分解が順調に進んでいることを確認できて、今年の品質への期待が高まります。土壌中では目に見えない小さな生き物たちが、美味しいみかん作りに貢献してくれているのです。

畑の守護樹 – 琵琶の実り
みかん畑の一角に、木陰を作るために植えている琵琶の樹があります。この琵琶の樹も今年は豊作で、オレンジ色に熟した実をたくさんつけています。初夏の太陽に照らされた琵琶の実は、まるで小さな灯籠のように美しく輝いています。
琵琶の樹は、みかんの作業の合間の休憩場所として重要な役割を果たしています。夏の強い日差しの中での作業では、木陰の存在は貴重です。また、琵琶の実は作業の合間の自然のおやつとしても楽しめます。

憎き天敵 – ゴマダラカミキリムシの脅威
6月に入ると、農家にとって最も恐ろしい害虫の一つ、ゴマダラカミキリムシが姿を現し始めます。この昆虫は斑模様を持つ大型のカミキリムシですが、みかんの木にとっては致命的な敵です。
ゴマダラカミキリムシの成虫は、みかんの樹皮を食い荒らし、樹幹に卵を産み付けます。孵化した幼虫は樹体の内部を食害しながら成長します。この内部からの食害により、養分の通り道である維管束が破壊され、最終的には木全体が枯死してしまいます。
一本のみかんの木を育てるには長い年月がかかります。苗木から植えて収穫できるまでに5-7年、本格的な収穫量になるまでには10年以上を要します。その大切な木が、この害虫によって一気に失われてしまう可能性があるのです。
ゴマダラカミキリムシの成虫は6月から7月にかけて活動が活発になるため、この時期の駆除が非常に重要です。早朝や夕方の涼しい時間帯に畑を巡回し、成虫を見つけ次第捕殺する必要があります。また、産卵痕を発見した場合は、速やかに処理することが求められます。

観察の重要性 – 梅雨時期の悲喜こもごも
6月の梅雨時期は、まさに観察が最も重要な時期です。高温多湿の環境は、病害虫にとって理想的な繁殖条件となるため、小さな変化も見逃すことはできません。
毎日の畑の観察では、悲喜こもごもの発見があります。若葉の順調な成長や肥料の良好な分解状況を見つけた時の喜び。一方で、病気の兆候や害虫の発生を発見した時の心配。琵琶の実の美しい実りに心和む瞬間と、ゴマダラカミキリムシを発見した時の緊張感。
このような日々の観察の積み重ねが、最終的な収穫の品質と量を決定します。問題の早期発見・早期対応が可能になれば、被害を最小限に抑え、適切な管理により品質向上を図ることができます。
観察には経験と知識が必要です。どのような変化が正常で、どのような変化が異常なのかを判断するには、経験が欠かせません。また、病害虫の生態や発生条件に関する知識も重要です。
匠の先生、先輩、JAの営農指導員さんから常にインプットしておりますが、やさしくいつでも教えて下さるので本当に助かります。感謝申し上げます。
雨の合間の作業 – 草刈りと防風林の剪定
梅雨の時期は雨が多く、屋外作業の時間が限られます。しかし、この時期にしかできない重要な作業もあります。雨の合間を縫って、草刈りや防風林の剪定作業を進めています。
草刈り作業は、畑の環境管理において重要な作業です。雑草は害虫の隠れ家となったり、病気の感染源となったりする可能性があります。また、みかんの木との養分競合も避けなければなりません。
しかし、すべての雑草を完全に除去するのではなく、生態系のバランスを考慮した管理を心がけています。一部の雑草は天敵昆虫の住み家となり、自然な害虫抑制に貢献してくれます。どの雑草を残し、どの雑草を除去するかの判断も、経験が重要になります。
旺盛な草は草刈り機で刈り払い、旺盛に大きくなる雑草は除草剤で抑止しています。
防風林の剪定も重要な作業の一つです。防風林は台風などの強風からみかんの木を守る重要な役割を果たしていますが、害虫(チャノキイロアザミウマなど)の生息場所にもなります。適度な剪定により、防風効果を保ちながら害虫の繁殖を防止することができます。
これらの作業は重労働で、特に梅雨時期の高湿度環境では体力の消耗も激しくなります。しかし、雨が降り始めれば作業を中断せざるを得ないため、晴れ間を見つけて効率よく進めています。
天候との駆け引き – 作業計画の調整
梅雨時期の農作業は、常に天候との駆け引きです。天気予報とにらめっこしながら、限られた晴れ間に最も重要な作業を優先的に進めなければなりません。
薬剤散布は散布後24時間は雨が降らない日を選ぶ必要があります。一方、肥料の効果を高めるためには、施肥後に適度な雨が欲しい場合もあります。このような相反する条件を同時に満たすタイミングを見つけるのは、まさに自然との対話といえるでしょう。
また、作業の優先順位も天候によって変わります。病害虫の発生状況、作物の生育状況、天気予報などを総合的に判断し、その日その日で最適な作業計画を立てる必要があります。
微生物との共生 – 土壌生態系の重要性
6月の畑で特に感じるのは、目に見えない微生物たちの重要性です。肥料を分解してくれるカビ、土壌の団粒構造を作ってくれる細菌、植物の根と共生して栄養吸収を助けてくれる菌根菌など、多くの微生物がみかん栽培を支えています。
化学肥料や農薬に頼りすぎると、これらの有益な微生物相が破壊される可能性があります。そのため、可能な限り有機質肥料を使用し、必要最小限の農薬使用に留めることで、土壌生態系の健全性を保つよう心がけています。
まとめ – 6月初旬 畑の物語
6月初旬のみかん畑は、生命力に満ち溢れた季節です。若葉の力強い成長、世代交代を迎える古い葉、病害虫との闘い、果実の自然淘汰、微生物による肥料分解、そして農家の日々の観察と管理。これらすべてが複雑に絡み合いながら、最終的に美味しいみかんという結果に結びついていきます。
この時期の観察と管理が、秋の収穫の品質を大きく左右します。一つ一つの小さな変化を見逃さず、適切な対応を続けることで、皆様に満足していただけるみかんを育ててまいります。
自然との対話を続けながら、伝統的な知識と現代的な技術を組み合わせて、より良いみかん作りに取り組んでいきます。6月の畑の物語は、まだ始まったばかり。これから本格的な夏を迎え、さらに多くのドラマが待っていることでしょう。
※当園では、こだわりの和歌山みかんを産地直送でお届けしています。9月末から出荷を始めますのでお楽しみにしてください。 メルマガに登録頂けますと受注開始のご案内をさせて頂きます。宜しければ登録をお願い致します。
メルマガ登録はこちら→https://mikan-kitabun.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new