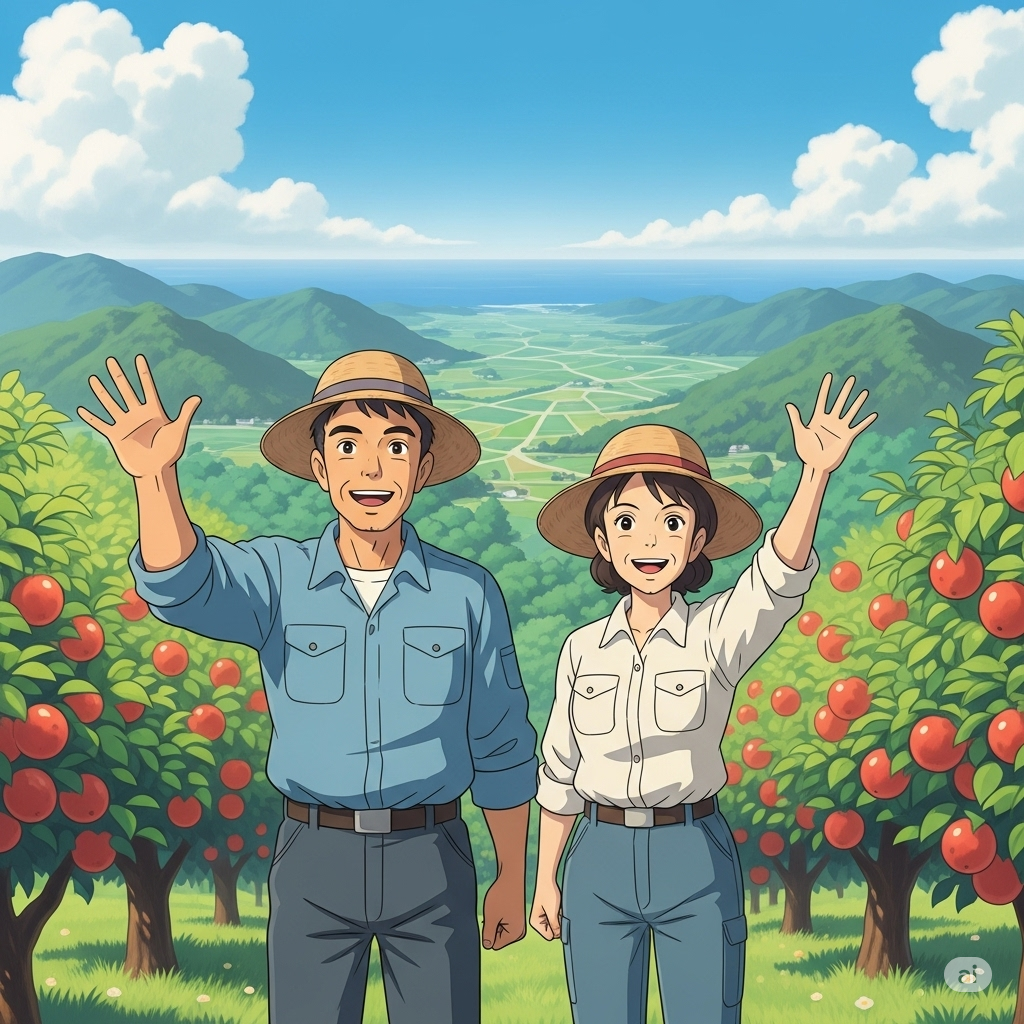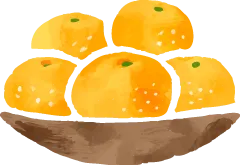私は現在、和歌山県海南市下津町でみかん農家を営んで5年目となりました。かつては他県でサラリーマンとして働き、50歳で早期退職し、家業であるみかん農園を継ぐ決断をしました。今回は「なぜサラリーマンを辞めてみかん農家を継いだのか」「農業という生業に必要なこと」「作物の選び方」について、自身の体験を通じて綴りたいと思います。
きっかけは「母の老い」と「家業への葛藤」
私が40代になったころ、父が体調を崩してしばらくして他界し、母がひとりで畑の管理を続けていました。年々老いていく母の姿に、他県で会社勤めをしている自分に対して、申し訳なさと焦りのような気持ちが募っていきました。
みかん農家として生きてきた両親が守ってきた畑。季節ごとに母から届くみかんは、会社の同僚にお裾分けしていましたが、誰もが「美味しい」と言ってくれました。そんな声を聞くたびに「この味を、これからも届け続けたい」という気持ちが芽生えました。
元々、50歳を一区切りにセカンドキャリアを考えていた私は、会社の早期退職制度を活用して、農家としての新たな人生に踏み出すことにしました。
志を胸に、慣れ親しんだ故郷での再出発
農業経験のない状態でのスタートでしたが、子どもの頃から慣れ親しんだ土地での再出発は心の安心に繋がりました。地域の先輩方や篤農家さん、農協の営農指導員の方々、肥料屋さんといった「人との出会い」が、今の自分を支えてくれています。
特に、会社時代の同僚や古い友人たちが私のみかんを購入してくれ、感想を届けてくれることが励みになっています。そして新たに縁が繋がって広がっていくお客様からの「美味しい」という声が、何よりの励みとなっています。
承継農家と新規就農者の違い――「環境」の有難さ
私は曾祖父の代から続く農家を継いだ承継農家です。畑や倉庫、水源、農機具、そして販路――これらの基盤が既に整っていたおかげで、比較的スムーズにスタートを切ることができました。
対して、新規就農者にとっては、こうした「モノ」をゼロから揃える必要があります。特に水源の確保や、作業場・倉庫の準備には大きな労力と資金が必要です。交通やアクセスのよい土地は競争も激しく、条件に合う環境を見つけるのは簡単ではありません。
その意味で私は、非常に恵まれた環境のもとで農業に挑戦できていると感じています。
作物選びは「自分の愛着」がすべてのスタート地点
農業を始めるにあたって、意外と見落とされがちなのが「何を作るか」という根本的な選択です。
私がみかん農家を継いだのは、家業だったからという理由だけではありません。みかんには、子どもの頃から親しみがあり、その味を心から美味しいと思っていたからです。そして、自分の育てたみかんを「美味しい」と言ってもらえる喜びが、農業という仕事の原動力になっています。
仕事というのは、楽しみながらでなければ上達しません。嫌々取り組んでいては、どんなに環境が良くても技術は身につかない。だからこそ「自分が愛着を持てる作物は何か」をよく考えるべきだと思います。
野菜を選ぶのか、果樹を選ぶのか、穀物を選ぶのか――それぞれに特徴と生活への影響があります。たとえば、四季折々に遠出の旅行をしたいというライフスタイルを望む人には、収穫や管理が頻繁に発生する野菜は不向きかもしれません。果樹は収穫が年に一度と少ないぶん、一年の成果を測る機会も少なく、技術の向上が実感しにくいという側面もあります。
また、高級フルーツのように繊細で手間のかかる作物を目指すのか、みかんのように比較的手に取りやすい価格帯で、幅広い層に親しまれる作物を作るのか。それによっても必要なスキルや販路戦略は変わってきます。
さらに、土地の土質や日当たり、水源の有無なども、適する作物を大きく左右します。理想だけで選ばず、土地に合っている作物は何か、地域で長年作られてきたものは何かといった視点でリサーチを重ねることが必要です。
「何を作りたいか」は、農業という仕事を続けていく上で、最も重要な問いのひとつだと私は思います。
「ヒト」「モノ」「カネ」――農業に必要な3つの要素
農業を生業とするには、「ヒト・モノ・カネ」の3つの要素が欠かせません。
ヒト(人)
家族の理解、取引先との信頼関係、地域の先輩方の支援、情報提供をしてくれる農協や業者さんとの連携――どれも欠かせない要素です。孤独になりやすい農業だからこそ、人とのつながりが持続の鍵になります。
私は他人から「人当たりは良い」と言われますが、基本的に人見知りでコミュニケーションをとるのは不得手です。対人関係を気にするのが煩わしくなったのも離職して就農した小さな要因の一つです。ですが、営農には土地での情報が不可欠です。天候特性、病害虫の盛衰、土質など、その点では農協さんの存在は大きいと思います。
モノ(物)
畑や倉庫、水源などのインフラがあるかどうかは、作業効率や収益性に直結します。これから農業を目指す方は、まずインフラ面の確認を徹底し、理想の土地が見つかるまでの間は農業法人等での経験を積むことも有効です。
カネ(金)
農業は自然に大きく左右され、収入が安定しにくい職業です。私の場合、早期退職制度を活用してある程度の資金を確保できたことが、就農の大きな後押しとなりました。無理のない営農計画と、健康管理を含めた長期的な視野が欠かせません。経験を積んで安定すれば、十分な生活基盤ができると思います。
農業という仕事の「やりがい」と「幸せ」
農業は一見「きつい」「大変」というイメージがありますが、その一方で、「美味しい」と言ってもらえる喜びや、自然と共に生きる充実感があります。
会社勤めの頃のように、他人に時間を縛られることはありません。天候や作物のリズムに沿って働くことで、心の健康が保たれていると実感しています。
農業は、ただ作物を育てるだけではなく、人とのつながり、自然との対話、そして「食の幸せ」を届けるという意味で、非常にやりがいのある職業だと私は思います。
最後に
50歳で会社を辞め、農家として新たな人生を歩み始めた私にとって、毎日は挑戦の連続ですが、それ以上に「出会い」と「喜び」に満ちた日々です。
家族や友人、お客様の「美味しい」の言葉が私の背中を押し、地域の人々との関わりが学びと支えを与えてくれています。
何より、自分が本当に作りたい作物に向き合い、誇りを持って届けられること。それこそが、私にとっての「セカンドキャリアの成功」のかたちだと思っています。