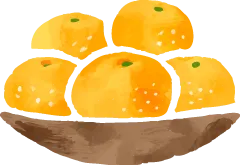こんにちは、北文園の北東です。6月に入り、梅雨の季節がやってきました。この時期は一年の中でも特に神経を使う時期で、天候に左右される作業が続きます。今回は、5月末から6月9日にかけての施肥と防除作業について、今年実際に体験した天候との闘いをお話しします。
肉カス有機配合肥料の施肥 – カビの力を借りた栄養供給
通常5月末から6月初旬にかけて、当園では肉カス有機配合肥料の施肥を行います。この肥料は単純に土に撒けば効果が出るものではありません。実は、肥料に含まれるタンパク質をカビの力によってアミノ酸に分解してもらい、そのアミノ酸を根から吸収してもらうという、まさに自然の力を活用した栄養供給システムなのです。
「カビ」と聞くと良くない場合が多いのですが、有機肥料を効果的に効かせるには重要なパートナーです。肉カス肥料に適切なカビが繁殖することで、タンパク質が根が吸収しやすいアミノ酸に変わります。このプロセスは化学肥料では得られない緩やかで持続的な栄養供給を可能にします。
さらに、カビが生えることで肉カス特有のにおいが消え、カラスなどの鳥類が肥料を食べ散らかすことも防げます。これは見た目の問題だけでなく、せっかく施した肥料が無駄になることを防ぐ重要な効果です。カラスは非常に賢い鳥で、肉の匂いを敏感に察知して群れでやってきます。一度狙われると、肥料を掘り返して食べ散らかし、園地が荒らされてしまいます。

カビを生やすための絶対条件 – 雨のタイミング
このカビを繁殖させるためには、施肥後すぐに雨が降ることが絶対条件です。適度な水分と温度があってこそ、有益なカビが繁殖し、肥料の分解が始まります。逆に言えば、雨が降らなければこの自然のシステムは機能しません。
天気予報とにらめっこしながら、雨が降る前に施肥を完了させる必要があります。しかし、ここに大きな問題があります。6月は梅雨入りの時期で、雨による病害虫の発生リスクが急激に高まる時期でもあるのです。
6月の病害虫リスクと防除の重要性
6月の梅雨時期は、みかんにとって一年で最も病害虫のリスクが高い時期です。主な脅威は以下の通りです。
黒点病は、雨によって胞子が飛散し感染する病気で、果実に黒い斑点ができ商品価値を大きく損ないます。梅雨の長雨は黒点病にとって絶好の感染条件となるため、雨が続く前に予防散布を行う必要があります。一度発生すると治療は困難で、その年の収穫に大きな影響を与えます。
チャノキイロアザミウマは、高温多湿を好む微小な害虫で、果実の表面に傷をつけて商品価値を下げます。6月の気候条件は彼らの繁殖に最適で、一度発生すると爆発的に増殖します。幼い果実は特に被害を受けやすく、この時期の防除が決定的に重要です。
カイガラムシは樹木に寄生し、樹勢を弱らせる厄介な害虫です。高温多湿の環境で活発になり、放置すると樹木全体の健康を害します。若い枝や葉に特に被害を与えるため、6月の防除は必須です。
これらの病害虫対策として、6月初旬には薬剤散布を行いたいのが本音です。しかし、ここで施肥とのタイミングの問題が生じます。
和歌山県編集 みかんの病害虫図鑑:https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070100/070109/gaiyou/002/byougaichuzukan/zukan.html
施肥と防除のジレンマ
肥料にカビが生える前に防除の薬剤散布をしてしまうと、肥料に薬剤が付着してカビの繁殖が阻害されてしまいます。これでは、せっかくの有機肥料の効果が台無しになってしまいます。
一方で、防除を遅らせすぎると病害虫の発生リスクが高まり、一年間の努力が水の泡になる可能性があります。まさに自然を相手にした農業の難しさがここに集約されています。
春肥(3月末)は、芽吹きと開花・結実と短期で成長のための養分消費が多い時は化学肥料で補給しています。
夏肥(実肥)は、夏の酷暑を乗り切る樹体づくりを行い果実への養分供給をしっかり行うため、アミノ酸が必須となります。そのため緩効性の有機肥料が最適と考え使用しています。
なんでやねん!- 予報が外れた5月末
今年は特に天候に翻弄された年でした。5月末に雨の予報が出たため、その雨に間に合うよう施肥作業を急ピッチで進めました。園地全体への施肥は重労働で、一人でやると数日かかります。雨予報を信じて、一日中汗だくで腰を庇いながら、なんとか雨が降る前に施肥を完了させました。
ところが、天気というものは本当に読めないもので、確実だと思われた雨予報が突然消滅してしまいました。施肥は完了していましたが、肝心の雨が降らない!!肥料は地面に撒かれたまま、カビの繁殖に必要な水分が得られない状況が続きました。
このような状況では、農家として焦りと不安が募ります。せっかく施した肥料が効果を発揮しないかもしれない、そして病害虫の発生時期は確実に近づいてくる。まさに板挟み状態でした。
6月9日の雨予報と3日間のタイムリミット
その後の天気予報を注意深く見守っていると、6月9日から雨予報が出ました。しかし、ここで新たな時間的制約が生まれました。当園は小規模ですが全園が手散布なので、全園への薬剤散布には3日間を要します。6月9日から雨が降るとすれば、8日までには散布を完了させる必要があります。
6月2日、施肥から約10日目、カビが少し生えているか?完全に全体にカビが回っていない!?汗。これは正直なところ、かなり厳しい条件でした。
頼りになるのは夜露と空気中の湿度のみ。6月の高湿度環境がせめてもの救いでした。
夜露と湿度に賭けた日々
雨が降らない日々が続く中、毎朝園地を見回りました。夜露がどの程度ついているか、肥料の状態はどうか、カビの繁殖の兆候はあるか。農家にとって、このような観察は日常ですが、今回は特に神経を集中させました。
幸い、6月の和歌山は湿度が高く、夜露も多少は期待できます。また、時折降る少量の雨(本格的な雨ではないが、少し葉を湿らせる程度)も助けになりました。
ギリギリセーフの散布実行
6月6日朝、肥料にカビが生え、匂いもほぼ消えていることを確認しました(そう判断した!)。本当にギリギリのタイミングでした。この日から3日間かけて、全園への薬剤散布を実施しました。
散布作業は早朝から開始します。
今回使用した薬剤は、黒点病予防のための抗菌剤「ジマンダイセン」と、チャノキイロアザミウマ・カイガラムシ対策の殺虫剤「アドマイヤ」「アプロード」です。使用量は最小限に抑え、環境への負荷を考慮した選択をしています。あとは液肥として「アミノ酸液肥」「微量要素を配合したミネラル系液肥」「緑化促進のMg」を混用して散布しました。
6月梅雨時期の重要性 – 一年を決める勝負の時
6月の梅雨時期は、みかん栽培において本当に重要な時期です。この時期を適切に管理できるかどうかで、その年の収穫量と品質が大きく左右されます。
高温多湿による病害虫の大発生リスク:梅雨の高温多湿環境は、多くの病害虫にとって理想的な繁殖条件です。一度発生を許してしまうと、爆発的に拡大し、制御が困難になります。
果実の幼弱性:6月の果実はまだ非常に幼く、外的要因に対する抵抗力が弱い状態です。この時期の被害は直接的に商品価値に影響し、回復も困難です。
若葉の重要性:新緑の季節でもある6月は、今年伸びた若い枝に新しい葉が展開する時期です。これらの若葉は、夏の光合成を支える重要な器官であり、来年の花芽形成にも大きく影響します。
若葉が健全に育つことで、夏の強い日差しに耐える光合成能力が向上し、樹勢が維持されます。また、充実した葉は来年の花芽分化を促進し、継続的な収穫を可能にします。
夏を乗り切るための基盤作り
6月の適切な管理は、厳しい夏を乗り切るための基盤作りでもあります。和歌山の夏は非常に暑く、みかんの木にとって厳しい環境となります。
この時期に施した有機肥料がしっかりと効いてくれることで、根系が充実し、夏の水分ストレスに対する耐性が向上します。また、病害虫から守られた健全な葉は、夏の光合成を支え、果実の肥大と糖度向上に寄与します。
来年への投資としての若葉管理
6月の若葉管理は、今年の収穫だけでなく、来年の結実にも大きく影響します。みかんは隔年結果の傾向があり、今年豊作だと来年は不作になりがちです。しかし、適切な栄養管理と病害虫防除により、この傾向を緩和することが可能です。
若葉が健全に成長することで、今年の果実への栄養供給がスムーズになり、同時に来年の花芽分化に必要な栄養も蓄積されます。これにより、安定した収穫を継続することができます。
自然と協働する農業の醍醐味と苦労
今回の経験を振り返ると、自然と協働する農業の醍醐味と苦労の両面を強く感じます。天候という制御不可能な要因に振り回されながらも、最終的に自然の力(夜露や湿度)に助けられて目標を達成できました。
自然のリズムを理解し、それに合わせて作業計画を調整する。時には自然に助けられ、時には自然に試される。
このような農業スタイルは手間も時間もかかり、リスクも伴います。しかし、得られる果実の品質と、そして何より農業本来の姿を実践できる満足感は、何物にも代えがたいものがあります。
今後への期待と課題
6月の難局を乗り越えた今、肥料がしっかりと効いてくれることを祈っています。カビによって分解されたアミノ酸が根から吸収され、樹勢向上と果実品質向上につながることを期待しています。
今後の課題としては、天候予報の精度向上への期待と、それに頼りすぎない柔軟な対応力の向上があります。また、有機肥料の効果を最大化するための土壌改良や、天候に左右されにくい施肥方法の研究も継続していきたいと考えています。
消費者の皆様へのメッセージ
このような苦労と工夫を重ねて育てられるみかんを、多くの皆様にお届けできることを心から嬉しく思います。単に甘くて美味しいだけでなく、環境に配慮し、土壌の健康を維持しながら育てられたみかんには、特別な価値があると信じています。
9月末からの出荷に向けて、これからも一つ一つの作業を丁寧に行い、皆様に満足していただけるみかんを育ててまいります。今年の天候との闘いが良い結果につながることを祈り、引き続き自然と協働する農業に取り組んでまいります。
おわりに
今回の6月の経験も、来年に活かせる貴重な学びとなりました。天候予報への対応方法、施肥と防除のタイミング調整、自然の力を活用した肥料管理など、多くの知見を得ることができました。
これからも、このような実体験を皆様と共有し、みかん栽培の奥深さと面白さをお伝えしていきたいと思います。そして何より、美味しく安全なみかんをお届けするために、日々努力を続けてまいります。
※当園では、こだわりの和歌山みかんを産地直送でお届けしています。9月末から出荷を始めますのでお楽しみにしてください。 メルマガに登録頂けますと受注開始のご案内をさせて頂きます。宜しければ登録をお願い致します。 メルマガ登録はこちら→https://mikan-kitabun.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new