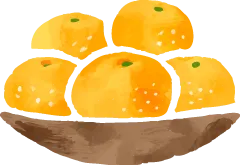秋から冬はみかんの収穫の準備だけ……と思われがちですが、実はここからが来季に向けた大切なスタートなのです。
北文園では、樹の状態を見極めながら、すぐに来年に備えた準備を始めています。
◆秋は「来年の枝」を育てる季節
気温が25度を下回るようになると、みかんの秋芽(あきめ)が止まります。秋芽が止まる前のタイミングを見計らって剪定を行うことで、来年の新芽の出方や花芽の付き方を調整していきます。
「裏年」で果実が少なかった樹は、翌年に多く花をつけやすくなります。そのため放っておくと、翌年に「実がなりすぎる」=「小玉で味が薄くなる」ことにつながるのです。
このバランスを取るために、秋のうちに花芽をあえて減らし、新芽を出しやすい環境を整えることが必要です。これが「裏年」「表年」の波を和らげ、毎年安定した品質を保つための大切な作業になります。
◆難しい「剪定」という作業
剪定は、みかん栽培の中でも特に難しい工程のひとつです。
どの枝を切るか、どれを残すか、その判断で翌年の果実の量も味も変わってきます。
北文園では、毎年講習会に参加して、篤農家の先生から指導を受けています。しかし、剪定の成果が見えるのは一年後。つまり「一年に一回しか答え合わせができない」世界です。経験と感覚を積み重ねながら、少しずつ精度を高めています。

◆秋剪定のポイント
秋の剪定では、「来年実をつけさせる枝」と「来年新芽を出させる枝」を見極めることが最も大切です。
-
下向きの枝や、黒ずんでしまった枝は切り落とす
- 主枝や側枝の流れを見て、樹全体が真っすぐ通るように整える
-
枝の表面に白い筋がある枝は、まだ勢いがある証拠(白筋が消えた枝は老化)
- 白い筋がある枝を水平になるように見出して芽出し剪定する
樹形を整えることで、養分の流れがスムーズになり、作業もしやすくなります。
また、白筋がしっかりある若い枝のうち、水平に伸びる枝を残すことで、来春の芽出しが安定し、次のシーズンの花芽形成につながります。
この「見極め」が難しく、積み重ねが美味しいみかんを育てるための根本です。

◆YN26は収穫を終えて「休眠期」へ
北文園で栽培している早生品種「YN26」も、収穫が終わるといよいよ休眠期に入ります。
果実を収穫し終えた樹は、栄養を使い切った状態。冬に向けてしっかり休ませるために、根が元気なうちに施肥(せひ)を行います。
この時期に施す肥料は「お礼肥」とも呼ばれ、樹に「今年もおつかれさま」という気持ちを込めて与えます。根が活動を止める前に、しっかり養分を吸収できるようにすることで、翌春の新芽の発芽を助け、枝の勢いを保ちます。

◆みかん栽培に「休み」はない
樹の様子を観察し、天候を読み、次の一年に備えて剪定や施肥を行う――。その積み重ねの先に、ようやく「美味しいみかん」が実ります。
和歌山・下津の温暖で雨が少ない気候は、みかんづくりに最適ですが、気候変動で近年は予測が難しくなっています。だからこそ、健康な樹に育てるための施肥、観察と手入れが欠かせません。
ひとつひとつの樹と向き合いながら、コツコツと手を入れていくこと。それが北文園の「美味しさの裏側」です。
◆おわりに
北文園では、これから冬を迎える園地で、剪定と施肥そして収穫の作業が続きます。来年も「和歌山・下津のみかんは美味しい」と言っていただけるよう、樹づくりの基礎をしっかり整えています。
今後も「みかん日記」を通じて、産地直送の現場から季節の様子をお届けしていきます。
ぜひ、定期便「つきイチみかん」やお得なポイント制度もご利用ください。
📦 箱で買ったみかんの保管方法について
👉 https://mikan-kitabun.com/methodforpreservingtanger/
※当園では、こだわりの和歌山みかんを産地直送でお届けしています。
🔸 会員登録でお得なポイント還元!
👉 https://mikan-kitabun.net/customer/login
🔸 メルマガ登録で受注開始やクーポン情報をお届け!
👉 https://mikan-kitabun.shop-pro.jp/customer/newsletter/subscriptions/new