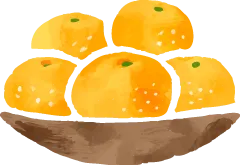秋に広がる病害虫の影──みかん農家の現場から
秋が深まり、下津町の山々も少しずつ色づき始めています。
この季節は、みかん農家にとって収穫に向けた重要な時期であると同時に、病害虫の発生にも注意が必要な季節です。今年は特に「ハナアザミウマ」の発生が多く、地域全体で被害が報告されています。

セイタカアワダチソウに集まる厄介者「ハナアザミウマ」
10月に入ると、耕作放棄地などで黄色い花を咲かせるセイタカアワダチソウが目立ち始めます。
この花に集まるのが、問題の「ハナアザミウマ」です。体長はわずか1〜2mmほどと小さいですが、花に集まる習性があり、主に花粉を食べます。
特に注意が必要なのが、極早生みかん(ゆら早生など)です。
セイタカアワダチソウの花が満開を迎える10月上旬から、極早生みかんの着色も始まります。花にだけ居てくれればいいのですが、色づき始めたみかんの果皮にも集まってきます。つまり、虫と果実のタイミングが重なることで、被害が一気に拡大してしまうのです。
ハナアザミウマに吸汁された果実は、果皮表面が茶色く変色し、時間が経つとそこから腐敗が進行します。見た目の傷だけでなく、加工用にもならない廃棄みかんとなります。
被害の現状と地域での対応
今年の下津町では、ハナアザミウマの大発生が報告されています。
青切りみかんとして出荷を行っている品種「YN26」は早めに収穫を終え、被害を免れましたが、10月中旬以降に収穫を迎える「ゆら早生」では大きな被害となっています。
一部の園地では、収穫したみかんの50%が廃棄となるケースもあり、農家にとっては深刻な打撃です。
私の園でも隣接する耕作放棄地があり、リスクを感じていましたが、幸いにもJAや先輩農家の方から早い段階で情報をいただき、「ディアナ」で防除対応を行うことができました。おかげで大きな被害は防げたようです。
ただし、町内ではすでにこの「ディアナ」も品薄になっており、今後の対策は早めの準備が必要です。病害虫対策は、タイミングと情報共有が命だと改めて感じます。

新たな脅威「アカマルカイガラムシ」の発生
もう一つ気になるのが、「アカマルカイガラムシ」です。
下津町では昨年あたりから近隣園地で発生が報告され、今年ついに自園でも1本の木で確認されました。
この虫は繁殖力が非常に強く、寄生密度が高まると枝が枯れ、最悪の場合は樹そのものが枯死します。果実にも寄生し、小さなカイガラ状の虫が無数に付き、見た目が悪くなり販売できなくなります。これもまた、経営への打撃は大きいです。
発生を確認した枝や果実、葉はすぐに切除し、焼却処分しました。来季早々にはマシン油による初期防除を取り入れ、防除計画を立てる予定です。感染の拡大を防ぐためには、早期発見と徹底的な除去が何より重要です。

気候と虫の関係──自然のリズムを読む
病害虫の発生は、気温や湿度と密接に関係しています。
篤農家の先生によると、虫の動きは暦や歳時記にほぼ合うとのこと。
桜の開花が気温で決まるように、害虫の発生にも自然のリズムがあるようです。
たとえば、秋に気温が下がり始め、一定の気温を下回ると植物の実りが進み虫も活動が上がるようです。そして、秋の高温が長引くと、虫の発生期間もそのぶん長くなってしまうのですね。
まさに今年のように、秋の暑さが続く年は要注意。
虫にとって活動しやすい期間が長くなるため、被害の拡大につながります。自然と向き合う農業では、気象の変化を読み取り、先手を打った防除が欠かせません。
生産者としての想いを綴る
病害虫との戦いは、毎年形を変えて訪れます。
それでも、私たちは「美味しい和歌山のみかん」を届けたいという思いで、一つひとつの課題に向き合っています。
防除も、ただ薬を使うだけではなく、タイミング・周辺環境・栽培方法などを総合的に考えることが大切です。
耕作放棄地が増える中で地域の協力も欠かせません。情報共有と早期対応があってこそ、被害を最小限に抑えられます。
下津の気候とともに生きるみかんづくり。
今年も自然と対話しながら、次の季節へと歩んでいきます。
関連記事
箱で買ったみかんの保管方法について
👉 https://mikan-kitabun.com/methodforpreservingtanger/
※当園では、こだわりの和歌山みかんを産地直送でお届けしています。
会員登録いただくと、お得なポイント還元を実施中です。
▶ 会員登録・ログインページはこちら
メルマガにご登録いただくと、受注開始のご案内やクーポン情報をお届けします。
▶ メルマガ登録はこちら
生産者としての想いを綴る──みかん日記は日々更新中。
ブログを通して、下津町から「みかんづくりの現場」を発信しています。