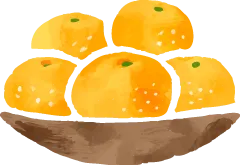いつも北文園のみかん日記をご覧いただき、ありがとうございます!和歌山県下津町でみかん農家を営む北東です。2月下旬から3月にかけて、みかんの木の剪定作業に励んでいます。
今年も、地元の匠であるベテラン農家さんの剪定講習を受講して、家に帰ってからはJAながみねの剪定動画で復習して、剪定技術の向上を目指しています。しかし、実際に剪定を始めると、教科書通りにはいかない難しさに直面し、日々悪戦苦闘しています。

剪定は奥が深い!
剪定は、みかんの木の形を整え、風通しや日当たりを良くすることで、病害虫の発生を抑え、美味しいみかんを実らせるために欠かせない作業です。
なぜ美味しいみかんになるのか?
日当たりと風通しを良くすると病害虫の発生を予防!はわかります。
美味しいみかんになるのに日当たりも重要ですが、適正な着果量になることが重要なんです。夏に摘果して調整もしますが、この時期に適切な剪定をすることで猛暑下での作業を軽減できるんです!
師匠であるH氏は夏に摘果が不要で、枝吊り(果実の重みで垂れ下がらないよう枝を支持して、日照確保と風キズ予防が目的)に専念されます
しかし、どの枝を切るか、どの枝を残すか、その判断は非常に難しく、長年の経験と知識が求められます。
特に、私が苦労しているのは、以下の点です。
- 花と芽のバランス:美味しいみかんを実らせるための、花芽と葉芽の最適なバランスの見極め
- 芽出し剪定:日光を効率よく取り込むための予備枝(葉芽を出させる水平枝)の配置の調整
- 悪癖(未熟):鋏を多用しすぎて切り込みすぎる
剪定の手順(備忘録)
剪定作業をスムーズに進めるために、自分なりに手順を整理してみました。
- 主枝の見極め:木の中心から勢いよく伸びる、丈夫な枝を主枝(3~4本)として見極める
- 整枝:主にノコギリを使って、不要な枝(逆行枝、枯れ枝、込み合った枝など)を取り除く
- 結果母枝と果梗枝のバランス:結果母枝(花芽をつける枝)と果梗枝(新芽をつける枝)のバランスを見て、花芽が多すぎる場合は、芽出し剪定を行います
整枝(樹形を整える)
- 【主枝の選定】:主枝と競合する枝を除去
- 【花芽と葉芽のバランスの見極め】:花芽を減らし芽出し剪定を行う。葉芽が多ければ花芽を減らさないように剪定を控えるか、邪魔な枝をのこぎりで除去するのみとする。
≪夏芽・秋芽が出ていれば花が多いと判断する≫ - 【亜主枝の先端を選定】:株元からスムーズな養分の流れをイメージして、亜主枝の先端に向けての流れを確認する
- 【のこぎりを用いて不要な枝を除去】:●主枝と亜主枝を結ぶ線上からはみ出す枝を切り戻す。●亜主枝の先端から左右45度の角度の線上からはみ出す枝を切り戻す。●逆行枝、被さり枝、競合枝を除去する。
≪第一亜主枝と第二亜主枝の上下間隔、先端の長さの違いはのこぎり一本分を目安≫ - 【樹勢が弱っている樹、樹冠内が空洞化している樹】:のこぎりを用いて切り戻しを行い若返らせる
剪定(花芽と葉芽のバランスを整えて着果量を調整)
- 【芽出し剪定】:花芽過多の場合に行う。果梗枝(昨シーズンに結実した枝)を探しつつ花芽とのバランスを確認する。果梗枝からは確実に芽が出るので、この枝を利用して予備枝を設定する。なければ青筋の入った充実した枝で水平な予備枝を設定する
≪花芽と葉芽は1:1≫ - 【切り過ぎない】:剪除する枝・葉は全体の20%。のこぎりを主体とすること(私の場合)
- 【枯れ枝の除去】:黒点病の発生源となるので除去する


匠の技に学ぶ
剪定講習では、匠が長年培ってきた技術を間近で見ることができ、大変勉強になりました。特に印象的だったのは、迷いのない剪定です。匠は、木の全体を見渡し、瞬時にどの枝を切るべきか判断します。その姿は、まさに職人技でした。
私も、匠のように、自信を持って剪定できるようになりたいです。そのためには、経験を積むしかありません。一本一本、丁寧に剪定し、みかんの木と向き合っていきたいと思います。
JAながみね:剪定動画https://www.youtube.com/watch?v=pLR6YMVTvXE
美味しいみかんのために
剪定は、地道で根気のいる作業ですが、美味しいみかんを作るためには欠かせません。剪定の出来が、その年の収穫を左右すると言っても過言ではありません。
これからも、剪定作業の様子や、みかんの成長日記などを、ブログで発信していく予定です。ぜひ、応援してください!